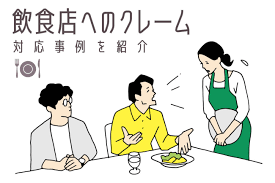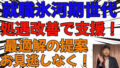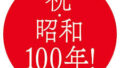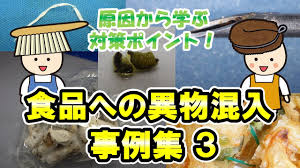
もう、最近の飲食店の異物混入問題、ほんまに多すぎてかなわんわ!ワシも昨日、テレビ見てたら「また出た!有名チェーン店で髪の毛混入!」言うてて、「あらあら、また始まったわ」思うたわ。せっかくの外食が台無しになるし、ちょっとでもSNSに上げられたら、もうその企業さん大変なことになるわよね。
私ね、30年以上食品業界見てきたけど、この異物混入問題、昔からあったのに今になって急に目立つようになったのはなんでかなーって考えたんよ。今日はそんな飲食チェーンでよく起こる異物混入の本当の理由と、これからどうしたらええのかをおばちゃんが徹底解説するわ!長いけど最後まで読んだら、あんたも「なるほど!」って思うはずやから、付き合うてな〜!
😱 異物混入が起こると何が大変なん?
まずはね、異物混入が起こるとどんな大変なことになるか、ちょっと考えてみましょか。
先月もあったわよね。あの大手ハンバーガーチェーンの商品から金属片が出てきたってニュース。ワシがその会社の社長やったら、もう夜も眠れへんわ!だって考えてみ?たった一個の金属片がお客さんの口に入ったってだけで:
- お店の信頼ガタ落ち
- SNSで「もう二度と行かへん!」の嵐
- テレビやネットニュースでボロクソに叩かれる
- 売上がガクンと落ちる
- 最悪の場合、全店舗休業もありうる
昔やったらね、「あ、すんません、髪の毛入ってました」で済んだかもしれんけど、今の時代はあかんのよ。スマホ一つでパシャっと写真撮って、ツイッターやインスタに「見て見て!こんなん入ってた!#〇〇チェーン #異物混入 #拡散希望」って上げられたら、もうそれだけで数十万、数百万人に見られるんやから。
わての友達の娘さんがコンビニでバイトしてるけど、「今はちょっとでもクレームきたらすぐに本社から電話かかってくる」言うてたわ。それくらい企業側も神経とがらせてるねん。
🤔 なんで飲食チェーンに限って異物混入が多いん?
「でもおばちゃん、なんでわざわざチェーン店ばっかり狙われるん?」って思うやろ?
そこがミソなんよ。狙われてるんちゃうねん。構造的に起こりやすい環境があるんや。ほな、ワテが長年見てきた飲食業界の裏側、ぶっちゃけたるわ!
1. 大量調理のリスク〜時間との戦いや〜
チェーン店ってのはね、朝から晩まで大量の食事を短時間で作り続けるんよ。ランチタイムなんか特に大変!行列できてるし、キッチンではバタバタ。「早く出せ出せ!」ってプレッシャーかかってる中で、ちょっとでも気を抜いたら…ほら、異物混入の元やね。
ワシの姪っ子が某ファミレスでバイトしてた時の話。ランチピーク時に「あと10分待ちです」って言うたら、お客さんから「なんでそんなに遅いねん!」って怒られたんやて。そういう状況下では、「早く出すこと」が最優先になって、「確認する時間」が削られるんよ。
たとえば、サラダ作る時でも、普通なら「よし、レタスに虫おらんか?」ってチェックする時間があるはずなのに、「急げ急げ!」の環境では難しい。そらもう、「急いては事故のもと」なんよ。
2. お店の人手不足問題〜教育が追いつかへんねん〜
今の飲食業界、人手不足が深刻なんは常識やわ。コロナ禍でさらに悪化して、今や中学生でも「ウチで働きませんか?」って声かけられるくらいやねんて(冗談やけど、そのくらい切羽詰まってるとこ多いねん)。
こないだ行ったラーメン屋でも、高校生くらいの子がオロオロしながら接客してたわ。悪いのはその子やない、教育する時間取れてないお店側の問題やね。
バイト入れ替わりも激しいから、マニュアル読んで「はい、明日から現場!」みたいな無理な状況。ほんまに基本的な衛生管理(手洗いの仕方、帽子の被り方、手袋の使い方)すら教わる時間ないんよ。
ワテの知り合いのお店では「髪の毛が落ちるのを防ぐために、髪の毛をまとめる練習から教育する」言うてたけど、そんな丁寧な教育できるチェーン店、今どれだけあるかな?
3. 調理と提供が別々〜責任の所在があいまいに〜
最近の飲食チェーンは、セントラルキッチンっていう大きな工場で作ったものを各店舗で温めたり盛り付けたりするシステムが多いねん。これがまた曲者!
「あれ?この弁当に虫が…」って言われても、それがセントラルキッチンで入ったのか、店舗で入ったのか、はたまた配送中に入ったのか…わからへんのよ。
責任の所在があいまいになると、自分ごととして考えにくくなるし、「うちじゃないから」って気持ちが生まれるのも人間の性(さが)よね。
🧐 形だけになってる衛生管理マニュアルの問題
「でもおばちゃん、ちゃんとマニュアルあるんちゃうん?」って思うよな。そうなんよ。立派なマニュアルはあるねん。でも、それが形骸化してるところに大問題があるんよ。
マニュアルあるけど守られてへん理由
- 忙しすぎて省略される:「手洗いは30秒以上」ってマニュアルに書いてあっても、お客さんが待ってたら「ちゃちゃっと5秒」で済ませちゃうんよ。
- 理解不足のまま現場へ:マニュアル読んだだけでは、なぜそれが必要なのか理解できへんまま作業することになる。「手袋は汚れたら交換」って言われても、「どの程度で汚れたと判断するのか」がわからへん。
- 古いマニュアルのまま:世の中どんどん変わってるのに、マニュアルが10年前のままなんてことも。新しい調理器具や食材が入ってきても、対応するルールがない。
ワテの友達がコンビニの店長してるけど、「毎日チェックリスト埋めてるけど、見るのはスーパーバイザーが月1で来た時だけ」って言うてたわ。それじゃあ、毎日やる意味あるんかいな?って思うよな。
そもそも現場の若い子らにとっては「なんでこんなめんどくさいことせなあかんの?」って思うだけで、マニュアルの意味がわかってないんよ。「これをやらないとどういう危険があるのか」の説明が足りてないのよ。
💪 ほな、どないしたらええねん?対策編
愚痴ばっかり言うてもあかんな。ほな、こういう問題をどう解決したらええのか、ワテなりの提案をさせてもらうわ!
1. 「なぜ?」がわかる教育を徹底しよう
マニュアルを読ませるだけやなくて、「なぜこれが必要なのか」を理解させる教育が大事やね。例えば:
- 「手洗いが不十分だと、お客さんが食中毒になる可能性があるよ」
- 「髪の毛一本でもお客さんの食欲を台無しにするし、SNSに上げられたら店の信頼も失うよ」
こういう理由をしっかり伝える教育をせなあかん。ワテは「百聞は一見にしかず」と思うから、実際に起きた事例を見せたり、「異物混入でクレームになった時、どんな気持ちになるか」を疑似体験させたりするのがええと思うわ。
2. チームで見守る体制を作ろう
一人の目では見落とすことも、複数の目があれば防げるもんよ。
- 調理担当と別の人が最終確認
- 盛り付け後に別の人が目視チェック
- 提供前に毎回声出し確認「異物なし!」
こういう多重チェック体制を作ることで、人間のミスを減らせるはず。でも、単に「チェックしろ」じゃなくて、「何をチェックするのか」「どうチェックするのか」まで明確にせなあかんよ。
3. 使えるマニュアルに進化させよう
紙のマニュアルだけじゃなく、動画やアプリを使った方がええと思うわ。今どきの若い子は字を読むより動画の方が理解しやすいらしいし。
それに、現場の声を取り入れて、実際に使いやすいマニュアルに更新していくことも大事やね。「これ、実際やりにくいよね」っていう声を無視せず、「じゃあどうすれば守れるか」を一緒に考える風土が必要やわ。
4. 問題が起きた時の対応を明確にしよう
どんなに気をつけても、ゼロにはできへんのが異物混入。だからこそ、発見された時の対応手順をしっかり決めておくことも大事やで。
- 誰に報告するのか
- お客さんにどう謝罪するのか
- 原因調査をどう進めるのか
- SNS対応はどうするのか
これらを事前に決めておけば、パニックにならずに済むし、二次被害も防げるんよ。
🌟 未来の食品安全はテクノロジーで変わる!
最後に、ワテは未来に希望を持ってるんよ。だって、今はええ時代やから!テクノロジーがどんどん進化して、人間の目に頼らない衛生管理ができるようになってきてるねん。
例えば:
- AIカメラで調理工程を監視して、異物が混入しそうな瞬間を検知
- IoTセンサーで厨房内の温度や湿度を常時管理
- タブレット端末で衛生チェックをデジタル化して、本部でもリアルタイム確認
うちの近所の回転寿司チェーンでは、もうレーン上を走る寿司をAIカメラで監視して、落ちたネタやゴミをすぐに検知するシステム導入してるらしいわ。これ、すごいと思わへん?
文化として根付かせることが大事
でもな、どんなにテクノロジーが発達しても、やっぱり最後は人の意識よ。トップから現場まで、「食の安全・安心は何よりも大事」という価値観を共有せなあかん。
うちの夫がよく言うてたわ。「会社の本気度は、社長がトイレ掃除するかどうかでわかる」って。衛生管理も同じこと。トップが本気で重要視してるかどうかが、現場の意識を変えるんよ。
😊 最後に、おばちゃんからのメッセージ
長々と読んでくれてありがとな!あんたらが安心して外食できる世の中になってほしいというのが、このおばちゃんの願いやねん。
飲食店の皆さん、大変やと思うけど、お客さんの健康と信頼を守るために頑張ってな!そして消費者のあんたらも、ちょっとした異物見つけた時、すぐにSNSにアップする前に、まずはお店の人に伝えてあげてな。改善のチャンスを与えるのも、ええ消費者の役目やと思うわ。
みんなが気持ちよく食事できる環境を作るために、お店も消費者も一緒に頑張りましょ!
それではまた、おばちゃんのブログを読みに来てな〜!
この記事は、食品衛生管理のプロフェッショナルである大阪のおばちゃんライターが執筆しました。情報は2025年4月時点のものです。