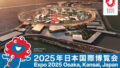いらっしゃい!今日も、奥さん、必見やで!「2025年タケノコ事情|関東は豊作・九州は不作の理由とは?」って、なにやら深刻そうなタイトルやけど、心配せんとって!いつもの調子で、面白おかしく、でもって、ホンマのところを深掘りしていくで!
2025年春の珍事件!?タケノコの「地域差」って一体どないなっとんねん!
いやいや、今年の春はホンマにビックリ仰天やで!タケノコ界隈が、なにやらエライ騒ぎになっとるらしいんや。「関東では、もぉ、これでもか!っちゅうくらいタケノコがニョキニョキ出てきて、スーパー行ったら二束三文やのに、九州では全然アカン!高くて手が出へん!」って、ホンマかいな!?って耳を疑うような話があちこちから聞こえてくるんや。
春の食卓のスター選手、タケノコに、なんでこんなにも地域差が出てきてるんやろか?実はなぁ、この背景には、自然界の不思議なリズム、「表年・裏年」っちゅうサイクルと、最近よう言われる「気候変動」の影響が、これまた深~く関わっとるらしいで。
特に九州のタケノコ農家さんは、頭抱えとるみたいやで。「今年はホンマに、土をいくら掘り返しても、ちょろっとしか顔出さへんのや…」って、泣きそうな声も聞こえてくる。そやのに、関東のほうでは、「今年は豊作すぎて、嬉しい悲鳴やわ!」なんて声も上がっとる。この“旬のズレ”は、一体何を意味するんやろか?
せやから今回は、この2025年春に起きたタケノコの地域差について、その裏側に隠された理由を、大阪のおばちゃん代表のこのワテが、あんたにもよ~く分かるように、じっくりと解説していくで!お茶でも飲みながら、ゆっくり読んでってな!
タケノコの旬と収穫サイクル、自然のリズムっちゅうもんは奥深いわ~
そもそも、タケノコの旬っちゅうたら、一般的には3月の終わり頃から5月の初め頃にかけてやんな。地域によって、ちょっと時期がズレたりはするけど、春の陽気に誘われて、土の中から顔を出すタケノコの姿は、ホンマに春の風物詩や。
せやけど、毎年必ず同じように、た~んと採れるとは限らへんのが、自然の面白いところやねんな。そこに登場するのが、「表年・裏年」っちゅう、ちょっとミステリアスな収穫サイクルや。
「表年」っちゅうのは、タケノコの収穫量がドーンと多い年のこと。前年に、親竹が栄養をたっぷり蓄えて、地下茎をグングン伸ばして、たくさんのタケノコを地面に送り出すんや。ほんで、「裏年」はその逆で、親竹がちょっとお疲れモードに入って、新しい芽の数が減ってしまうから、全体の収穫量がガクッと落ちてしまう年になるっちゅうわけや。
このサイクルはなぁ、大体1年おきにやってくると言われとって、タケノコ農家さんや山を管理してる人にとっては、まさに自然との静かなる対話みたいなもんやねんな。長年の経験で、「今年は表やな」「来年は裏やな」って、なんとなく分かるらしいで。
せやけど、最近はこのサイクルが、昔みたいにキッチリ1年おきに来るとは限らへんようになってきてるらしいで。その原因として、やっぱり「気候変動」の影響が疑われとるんや。地球の温度が上がったり、雨の降り方が変わったりすると、タケノコの成長のリズムも狂ってしまうんやろなぁ。
それに、タケノコの収穫量を左右するんは、表年・裏年だけやないんやで。冬場の気温がどないやったかとか、どれくらい雨が降ったか、春先の気温がいつ頃上がってきたか、っちゅうのも、めっちゃ大事な要素になるんや。つまり、タケノコの旬っちゅうのは、自然のいろんな条件が、絶妙なバランスで噛み合って、初めて生まれる“繊細な奇跡”みたいなもんやねんな。
なんでやねん!?関東でタケノコが豊作になった理由を深掘りしてみたで!
さてさて、今年の春、関東地方では、ホンマに信じられへんくらいのタケノコが採れて、市場や直売所はタケノコ、タケノコ、またタケノコ!特に、千葉県や茨城県あたりでは、3月中旬から本格的な収穫が始まって、4月の上旬には「例年の1.5倍くらいの出荷量になった!」なんて話も聞こえてくるくらいやから、ホンマにすごいこっちゃで。
この豊作の大きな理由の一つが、さっきも話した「表年」っちゅう収穫サイクルの影響やねん。関東地方では、去年の2024年が「裏年」で、タケノコの収穫量がちょこっと少なめやったんや。せやから、今年は、地下茎が栄養をた~っぷり蓄えて、親竹が元気いっぱいに活動する“当たり年”になったっちゅうわけや。自然の帳尻合わせみたいなもんやな。
それに加えて、去年の秋から今年の冬にかけての気象条件も、タケノコの成長にとって、これまた最高のコンディションやったらしいで。特に、冬の寒さが適度にあって、地中でタケノコの芽がゆっくりと、でも確実に準備を進めることができたんや。ほんで、春先になって、気温がグッと上がったおかげで、準備万端のタケノコたちが、一斉に地面から顔を出したっちゅうわけや。タイミングって、ホンマに大事やねんな!
地元の農家さんの話を聞くと、「今年は、掘っても掘っても、次から次へと出てくるんや!」ってみんなニコニコ顔やで。市場の価格も安定してるから、消費者も嬉しいやろうなぁ。地元のスーパーでは、「タケノコ祭り」みたいなイベントも開催されて、春の訪れをみんなで喜び合ってるみたいやで!ええなぁ、活気があって!
まさに、自然のリズムと、天候のええ条件がバッチリ合わさって、関東地方では2025年の春に、ホンマにラッキーな“タケノコの当たり年”がやってきたっちゅうことやな!
なんでやねん!?九州でタケノコが不作になった悲しいワケを探ってみたで…
一方、関東のウハウハ状態とは真逆で、今年の九州地方では、タケノコが全然採れへんくて、農家さんはホンマに困っとるみたいやで。特に、熊本や福岡、佐賀あたりでは、「1日に数本しか掘れへん」「例年の3割くらいの収穫量しかない…」なんて悲しい声が次から次へと聞こえてくる。地元の直売所や市場に行っても、タケノコが全然置いてへんかったり、あってもビックリするくらい高かったりするらしいで。春の味覚が、手の届かない存在になってまうなんて、ホンマに寂しい話やなぁ。
この不作の大きな原因の一つが、やっぱり「裏年」の影響やねん。九州地方では、去年の2024年が「表年」で、タケノコがようけ採れた年やった。せやから、自然のサイクルから考えると、今年は「裏年」になって、収穫量がガクッと減るのは、ある程度予想されとったことなんや。
せやけど、それに追い打ちをかけるように、今年の冬から春にかけての気候が、これまた最悪やったらしいで。去年の冬は、例年に比べて暖かすぎて、地中の温度がなかなか下がらへんかったんや。そうなると、タケノコの芽がしっかりと冬眠できひんくて、春になっても、なかなか元気に育たへんのや。
さらに、春先には雨が全然降らへん日が続いて、地中がカラカラに乾いてしもた。水不足は、タケノコの成長には致命的やからなぁ。これらの気候条件が、悪いことに重なって、ただの裏年やなくて、予想をはるかに超える大不作になってしもたっちゅうわけや。自然って、ホンマに気まぐれやなぁ…。
地元の農家さんの間では、「最近、気候が全然読めへんようになってきた」「裏年でも、ここまで全然採れへんのは初めてや…」って、不安の声が広がっとるみたいやで。タケノコ作りは、自然相手の仕事やから、ホンマに大変やろなぁ。将来のことまで心配になってまうわ。
単なる裏年っちゅう一言では片付けられへん、自然の複雑な変化が、今年の九州のタケノコ不作の陰には隠されとるんやなぁ。
地球規模の異変!?気候変動とタケノコの未来について、ちょっと真面目に考えてみたで
ここ数年、タケノコの収穫量とか、旬の時期が、今まで当たり前やと思っとった常識では、説明できへんような形で変わってきてるらしいで。その大きな原因として、やっぱり地球全体で進んどる「気候変動」の影響があるって言われとるんや。
タケノコはなぁ、冬の寒さでいったん成長が止まって、春になって気温が上がると、地面から顔を出すっちゅう、ホンマにデリケートな植物やねん。せやけど、冬の気温がなかなか下がれへん年が続くと、芽の休眠がうまくいかへんくて、芽が出るタイミングがズレてしまうことがあるんや。
それに、春先に急に気温が上がると、タケノコが一気に伸びすぎて、「えぐみ」が強くなったり、品質が落ちてしまうこともあるらしいで。せっかく出てきたタケノコが、美味しくなくなってしまうなんて、ホンマに悲しい話やで。
最近は、冬の暖冬傾向だけやなくて、春の急激な気温の変化、それに、局地的な干ばつや大雨なんかも増えてきて、自然環境が不安定になっとる。これが、タケノコの収穫量に大きな影響を与えてるんや。特に、九州みたいな温暖な地域では、その影響が顕著に出てるみたいで、これまでの経験だけでは、もう対応できへん場面が増えてきたらしいで。
研究者の間でも、「これまでの裏年・表年の考え方が、もう通用せんくなってきてるかもしれへん」なんて声も上がっとるみたいやで。これからは、もっと詳しい気象データに基づいて、タケノコの管理や収穫の予測をしていく必要が出てくるんやろなぁ。
つまり、タケノコっちゅう、自然からの大切な恵みは、もはやただの“気まぐれ”なもんやなくて、“気候のバロメーター”みたいな存在になりつつあるっちゅうことやな。地球の異変を、一番敏感に感じ取ってるのかもしれへんな。
ピンチはチャンス!?地域ごとの「旬」を賢く楽しむ知恵と工夫を伝授したる!
今年の春に見られたタケノコの地域差――関東は豊作、九州は不作っちゅう現象は、一見すると、ちょっと残念な話に聞こえるかもしれへん。せやけど、考え方を変えてみたら、これは「旬の味を、地域ごとに楽しむ」ええ機会やと捉えることもできるんやで!
例えば、関東では3月中旬から4月にかけてが、まさにタケノコの旬のピーク!市場や直売所には、新鮮なタケノコが手頃な値段でズラリと並んで、家庭の食卓でも「若竹煮」や「タケノコご飯」が登場する機会が増えるやろなぁ。
一方、九州みたいに不作の年は、地元の農家さんが、知恵を絞って、採れた少ないタケノコを、保存加工品や水煮なんかに力を入れて、無駄にせんと、長く楽しめるように工夫してる動きもあるらしいで。これも、また一つの生きる知恵やね。
それに、地域によって、タケノコの種類や味わいにも違いがあるんやで。京都の「白子タケノコ」は、柔らかくて上品な味わいやし、熊本の「孟宗竹」は、大きくて食べ応えがある。それぞれの土地の気候や土壌が、タケノコの味にも個性を持たせるんやなぁ。こういう違いを知ることで、ただ「豊作・不作」で一喜一憂するだけやなくて、「どこのタケノコが、いつ、どんな風に美味しいんやろ?」っちゅう、新しい視点が広がってくるやん!
最近では、旬の時期に合わせて、「タケノコ掘り体験」とか、「農家レストランでの筍づくし御膳」みたいな、体験型のイベントも各地で開催されとるらしいで。自然の恵みを、見て、触って、味わって、五感で楽しむっちゅうのは、ホンマに贅沢な体験やなぁ。
自然のリズムに寄り添って、それぞれの地域の特徴を知りながら、旬の味を大切に味わう――それが、これからのタケノコとの上手な付き合い方なのかもしれへんな。
追伸やで!
今回のブログでは、「2025年 タケノコ 不作 豊作」っちゅう旬の話題を中心に、地域差の背景にある自然のサイクルや気候変動、そして、そんな中でもどうやって楽しむか、っちゅう視点でお話させてもらったで。食べ物の情報は、ホンマに変わりやすいけど、タケノコみたいに、自然に深く根ざしたもんは、こういう背景にある物語を知ることで、もっと美味しく、もっと大切に味わえるようになると思うんや。
今年のタケノコを食べる機会があったら、ぜひ、その「背景」にもちょっとだけ思いを馳せてみてほしい。きっと、ただの食材やなくて、“自然からのメッセージ”が、そこにあるはずやから。ほな、今日はこの辺で!おおきに!